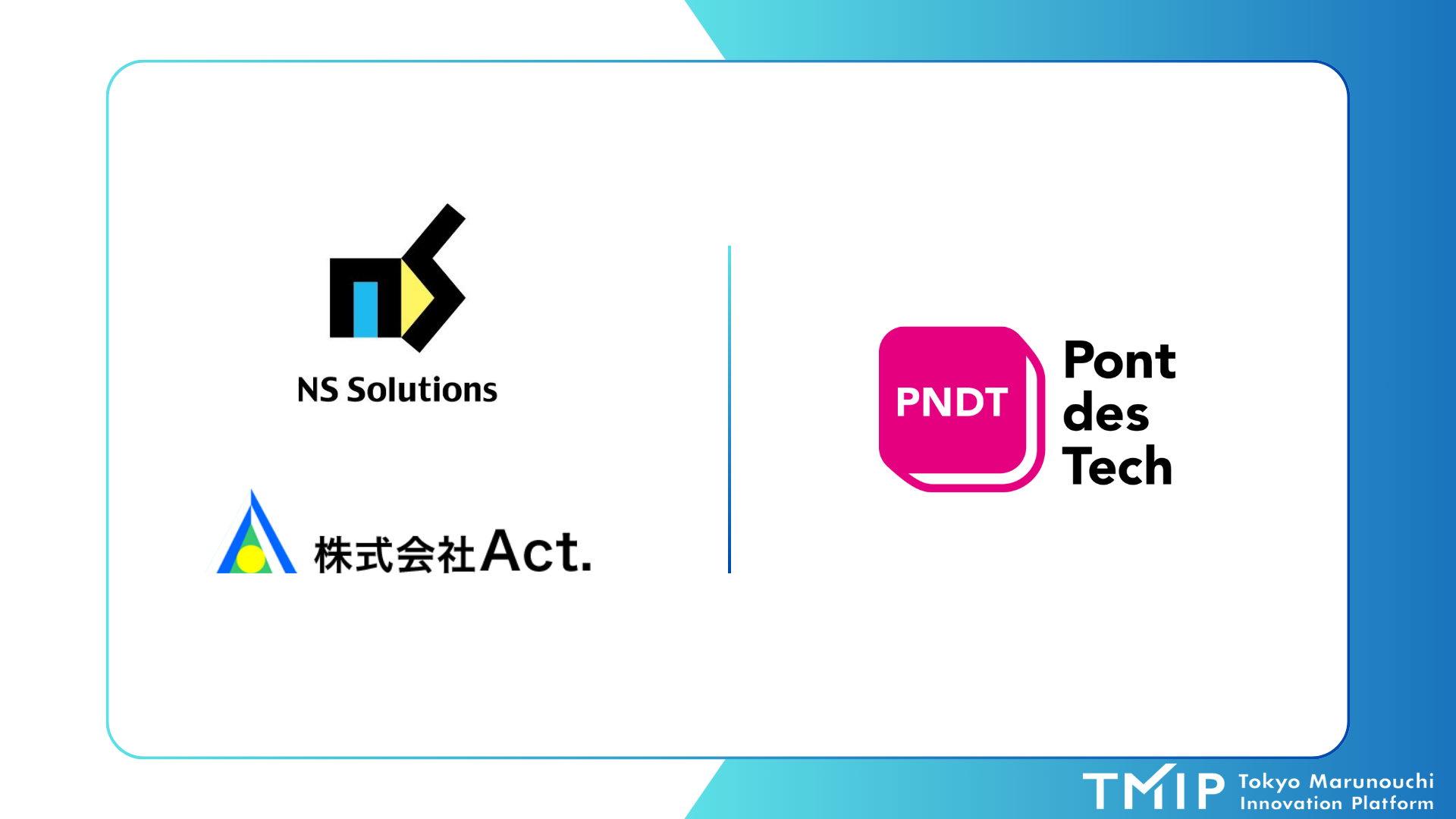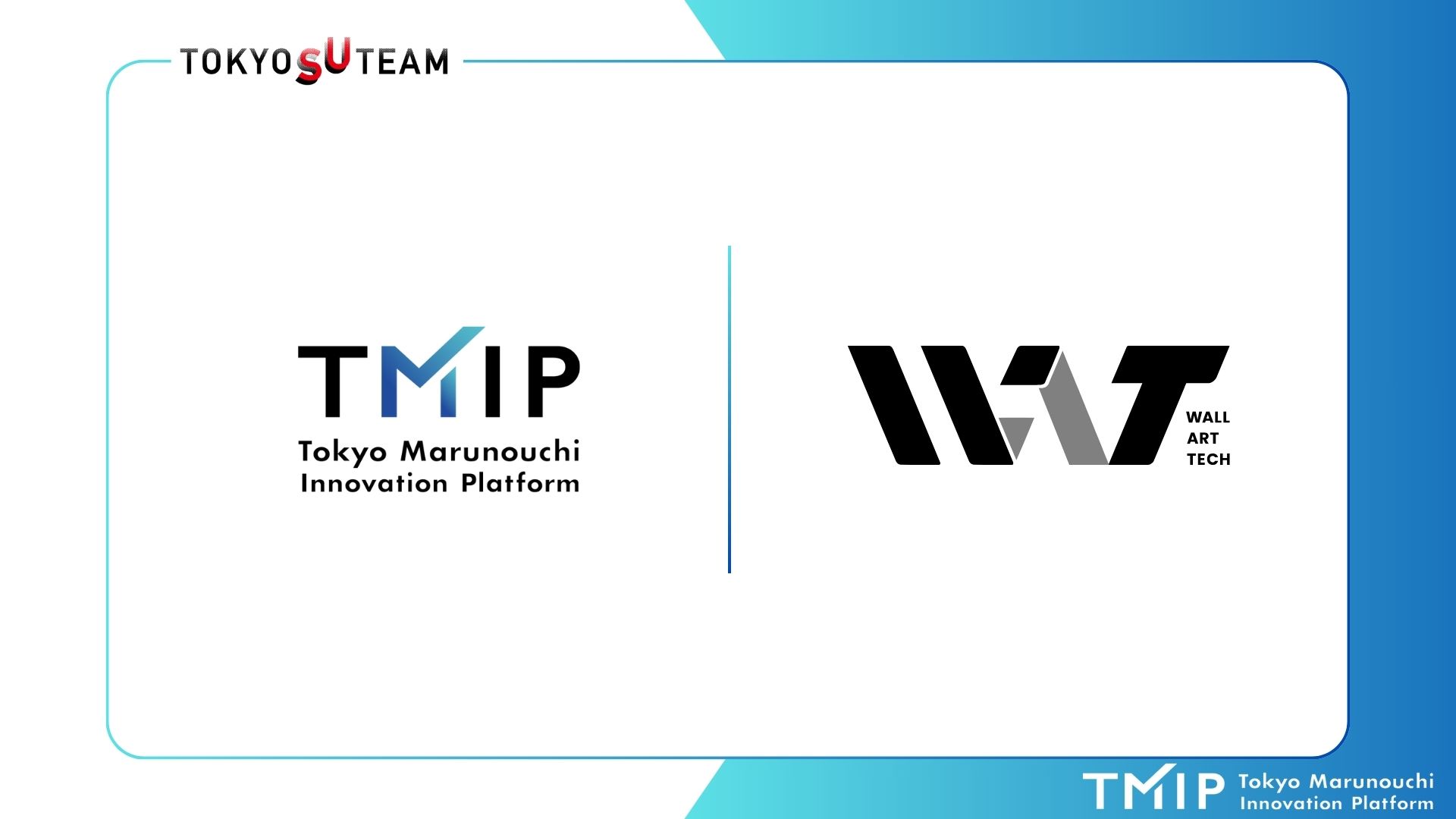ソーシャル・イントラプレナー・スクール
「2030年 ソーシャル・イントラプレナーの働き方がスタンダードになっている社会をつくる」というビジョンを掲げ開校した、日本初の“サステナビリティ人材育成プログラム”です。
企業は、社員のエンゲージメント向上と、社会課題への戦略的な対応を同時に求められています。従来の研修やエンゲージメント施策では、必ずしもこの課題に十分対応ができていません。社員一人ひとりの「ジョブクラフティング※」を促すとともに、「サステナビリティへの対応を企業価値に転換」できる人材が待ち望まれています。そんな人財を、「ソーシャル・イントラプレナー・スクール」は継続的に輩出し、職場に新しいムードをつくり出すとともに、事業を通じて日本と世界の課題を解決に導ける次世代の社内イノベーターを生み出していきます。
※ジョブクラフティング = 従業員が自分自身の意思で仕事を再定義し、やりがいのある仕事に変えていく手法
TMIPは、大企業の新規事業創出を支援するオープンイノベーションプラットフォームとして、現在350を超える団体が参加するコミュニティを形成しています。その中で、職種やテーマごとに課題を共有し合う場として定期開催されているのが「TMIPビアナイト」です。
2025年7月15日に開催された今回のビアナイトでは、「次世代型のイノベーター人材<ソーシャルイントラプレナー>社会課題を解決する社内起業家とは?」をテーマに、大企業で社会課題解決に取り組む2名のイントラプレナー、富士通株式会社の本多 達也さんとアサヒユウアス株式会社の古原 徹さんが登壇。ビールを片手にカジュアルな雰囲気の中、その実践と知見を共有しました。
富士通、アサヒビールにてソーシャルイントラプレナーとして活動してきた2人
最初に登壇したのは、富士通株式会社で「Ontenna(オンテナ)」プロジェクトのリーダーを務める本多 達也さん。Ontennaは、音の大きさを振動と光で伝える装置で、聴覚障害者と一緒に開発されたプロダクトです。
本多さん「Ontennaにはマイクが入っていて音を拾って振動します。大きい声だと強く振動し、小さい声だと小さく振動する。シンプルな機能ですが、これがあることで音のリズムが分かったり、大きさの強弱が分かったりします。Ontennaを使うと、聴覚障害の有無に関わらず、みんなで太鼓を叩いたり音楽を楽しんだりすることができます」
Ontenna開発のきっかけは、大学の文化祭での偶然の出会いでした。
本多さん「大学に入るまで周りにろう者の方がいなかったんですが、大学の文化祭でたまたまろう者の方が来て、そこで手話を使っていて『手話かっこいいな』というところから、手話通訳のボランティアを始めました」
その後、2014年に経済産業省の未踏プロジェクトに採択され、本格的な開発がスタート。現在では全国の約8割のろう学校で活用されるまでに普及しています。

イベント現地でも見せていただいたOntenna(https://ontenna.jp/)
続いて登壇したのは、アサヒビール株式会社のグループ会社であるアサヒユウアス株式会社に在籍している古原 徹さん。古原さんは、2021年に大ヒットした「生ジョッキ缶」の開発者として知られています。
古原さん「生ジョッキ缶の発想は、当初社内でほとんどの人に否定されました。役員にラボに来てもらって、実物を見てもらったら気に入ってもらえたので、提案に進んでいきました。2017年に開発に着手していたのですが、設備投資に数十億円規模の予算も必要になるため、GOサインが出るまで1年ほど待つ期間もありました」
苦労を乗り越えて開発した同商品がヒットする一方で、古原さんはもやもやした想いを抱えていたといいます。
古原さん「生ジョッキ缶は、飲み終わったらゴミになってしまいます。そのことに自分はもやもやを抱えていました。お客様が購入した後も、ゴミにならないビジネスを作れないかと考えたんです。いろいろと挑戦してきて、事業としても育ってきた。それで会社に『もう、こっちのビジネスにコミットしたいです』と言い続けて、アサヒユウアスという会社ができました」
現在は、アサヒユウアスにてサーキュラーエコノミーの観点から環境配慮型製品の開発に取り組んでいる古原さん。イベント当日も参加者に同社が開発している、目黒川の桜の剪定枝を使用したカップや、自然界のバクテリアで分解される「日本初、地球に還るコップ」などのサステナブルカップを配布してくださいました。
「ソーシャルイントラプレナー」として実績を作り出すまでの道のり
登壇者のおふたりの自己紹介が終わった後は、「ソーシャルイントラプレナー」という働き方をテーマに話が進みました。『SDGs時代のソーシャル・イントラプレナーという働き方』という著書を書かれ、次世代型のサステナビリティ人材育成プログラム「ソーシャル・イントラプレナー・スクール」も開校している本多さんは、この新しい働き方の意義をこう語ります。
本多さん「ソーシャルイントラプレナーというのは、企業のリソースというのをうまく活用して、社会課題に対してアクションする人たちです。この働き方のポイントは、個人としては自分がやりたい社会課題にチャレンジでき、働きがいの向上や組織とのエンゲージメント向上につながる点です。組織としても、これまでアクションできなかった領域にチャレンジできるため、双方にとっていい働き方なんじゃないかと考えています」
両氏とも、ソーシャルイントラプレナーとして活動を行っていますが、社内で理解を得るまでには苦労があったと振り返ります。
本多さん「最初、Ontennaは全然社内の共感を得られませんでした。富士通に入社して、3年ほどかけて取り組んで、研究と事業開発は違うと気づいて、どうやってビジネスにしていくか、社会的な価値をどう作っていくかに悩みました。
たとえば、お客様がろう学校だけでは事業にはならないという課題もあり、CSR的な活動になってしまうと、事業として成長させることが難しくなってしまいます。それに頭を悩ませていたときに、ろう学校の先生が『これでみんなで音楽楽しめるよね』というアイデアを出してくださって。そこからエンターテインメント領域で1回のイベントで数百万円規模で購入いただけるようになりました」
社内での理解を得るために効果的だったのは、外部からの評価でした。「外からの評価が中を動かすのが一番早い。例えば、アワードなども受賞すると社内での見る目が変わるから大事なんです。TMIP Innovation Awardを受賞できたことも大きかったですね」と本多さん。
古原さんの場合、そもそも社会課題への関心から始まったわけではありませんでした。
古原さん「元々、個人的には社会課題にあんまり興味はありませんでした。元々はどっちかというと、大企業内で勤務していると、自分がどれだけの価値を生んでいるのか分からない、というもやもやした気持ちを抱えていて。自分が作ったものを自分で売って、次に繋げてみたい、とずっと考えていました。
転機となったのは、社内評価で高評価を諦めたこと。会社に評価されることより、社会に評価されるアクションを選ぼうと、自分のスタンスを決めました。やりたいことに取り組んでいるのだから、会社の評価は気にしない姿勢で活動して、後から評価がついてきましたね」
「ソーシャルイントラプレナー」という大企業における新たな働き方の可能性
質疑応答の時間では、参加者から「なぜ、独立せずに大企業に留まるのか」という質問が投げかけられました。
本多さん「富士通という会社の看板があった方が事業はうまく進むことがあります。例えば、ろう学校を訪問した際に、『ベンチャー企業本多です』と自己紹介したら、相手は『本当に大丈夫か』と思ってしまいます。また、富士通にはこれまでものづくりの経験から製品の安全基準などについても相当ノウハウが詰まっています。このノウハウも活用できることは、良いものづくりを行う上でも利点になります」
大企業に留まって事業を展開することに利点があるという本多さんの意見に対して、古原さんも同様の見解を示しました。
古原さん「大企業の看板を使うと、様々な方とコラボレーションするにしてもハードルが下がります。自分にとって面白い仕事を形にしていけるので、辞めずに事業に取り組みたいですね。ただ、さらにスピードを上げて取り組めるといい場面もあり、そこは副業なども含めて、柔軟な働き方をしていきたいと考えています」
最後に、本多さんと古原さんのおふたりから、参加者へ向けてメッセージが投げかけられました。
本多さん「去年までデンマークに住んでいたのですが、デンマークでは投票率は86%近くになるんです。住んでいる間、どうやってそれだけ社会への信頼がある状態が実現できているのかを考えていました。日本ではどうできるかなと考えると、まず日本って社会に対する信頼が低いと思っています。政治と市民の距離がとても遠い。
一方で、会社に対しては信頼がある。だから、日本においては、会社を変えていくことを通じて社会全体を変えていけるのではないか、という希望を持っています。そのためにも、会社の中で社会的な課題の解決にチャレンジをする人たちを増やしていきたいですね」
古原さん「大企業での挑戦だって上手くいくんだってことをちゃんと社会に知ってもらいたいと思っています。だから、社外にも出ていくし、発信をしています。私は大企業が社会をよくできる、社会を変えられると思っているんです。自社で成功事例をつくって発信し、他の会社にも『うちもやってみよう』と考えてもらえたら、社会全体が良くなる方向に進むはず。そうやって次世代に向けて良い社会を残せるようにと挑戦しています」
最後にTMIPビアナイトのモデレーターを務めたTMIP事務局の大淵は「TMIP Innovation Awardで出会った本多さんが受賞後も活躍の場を広げ、次世代のイントラプレナーを増やす活動をされています。多様な働き方や新規事業創出の可能性があることを、TMIPコミュニティにも広げていきたいという熱い想いに共感して今回の企画が実現しました。アワードで終わらず、このようにご一緒できることを事務局として嬉しく思います。
会場からもたくさんご質問をいただきましたが、組織の中で新しい取り組みを始めるには様々な障壁があります。こうして本多さんや古原さんの経験やノウハウを共有することで新たな一歩を踏み出すきっかけとなれるようTMIPとしても交流の場を今後も提供してまいります」と語り、和やかな雰囲気の中イベントを締めくくりました。
質疑応答のあとは、ネットワーキングタイムに。交流の時間では、登壇者に質問を投げかける参加者の姿や、名刺を交換する姿が会場のあちこちで見受けられました。
TMIPは今後も、大企業の新規事業創出を支援し、社会課題解決に取り組むイントラプレナーたちの交流と共創の場を提供していきます。みなさまのご参加をお待ちしております!
<2人が講師を務める「ソーシャル・イントラプレナー・スクール」とは>