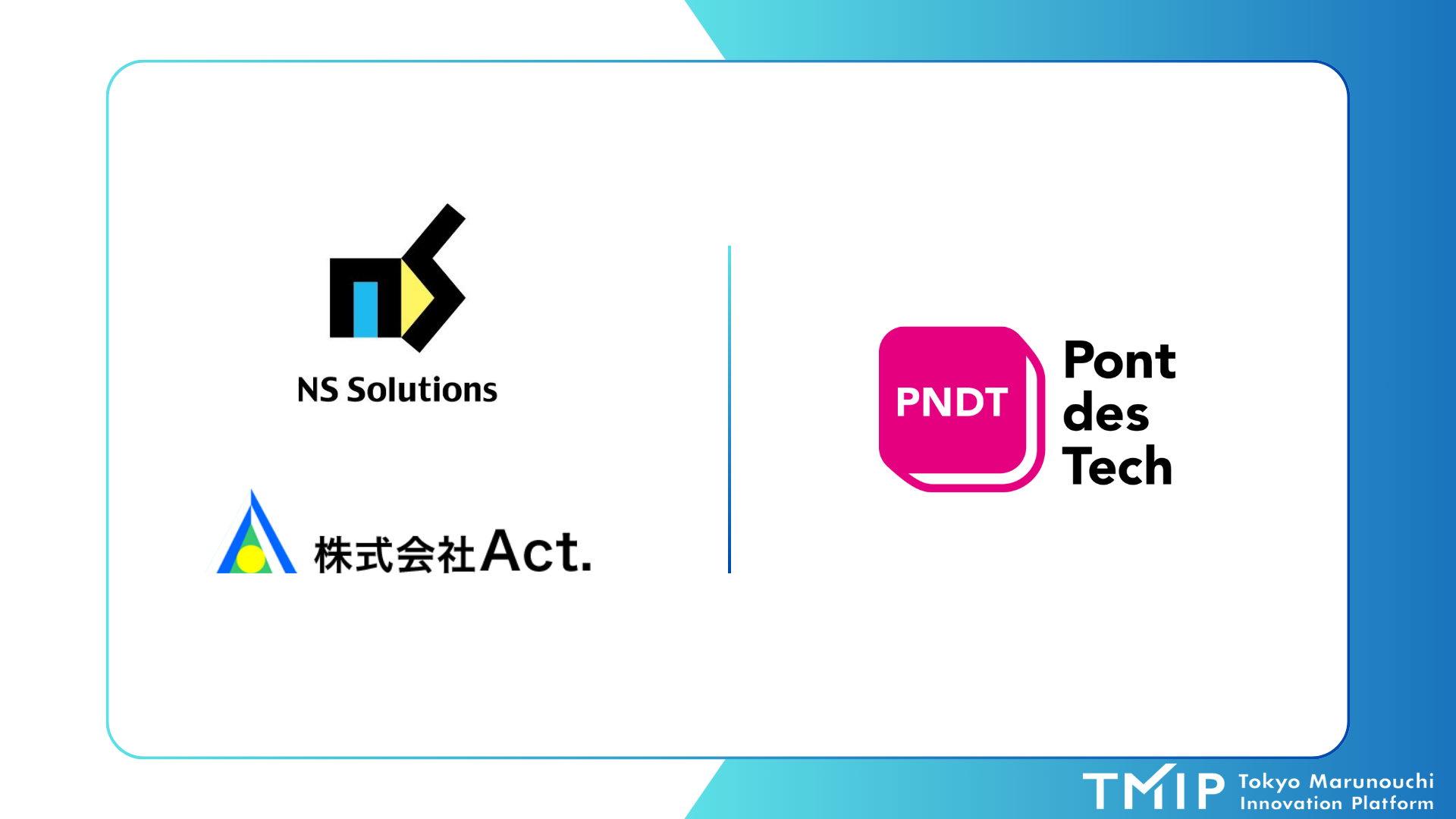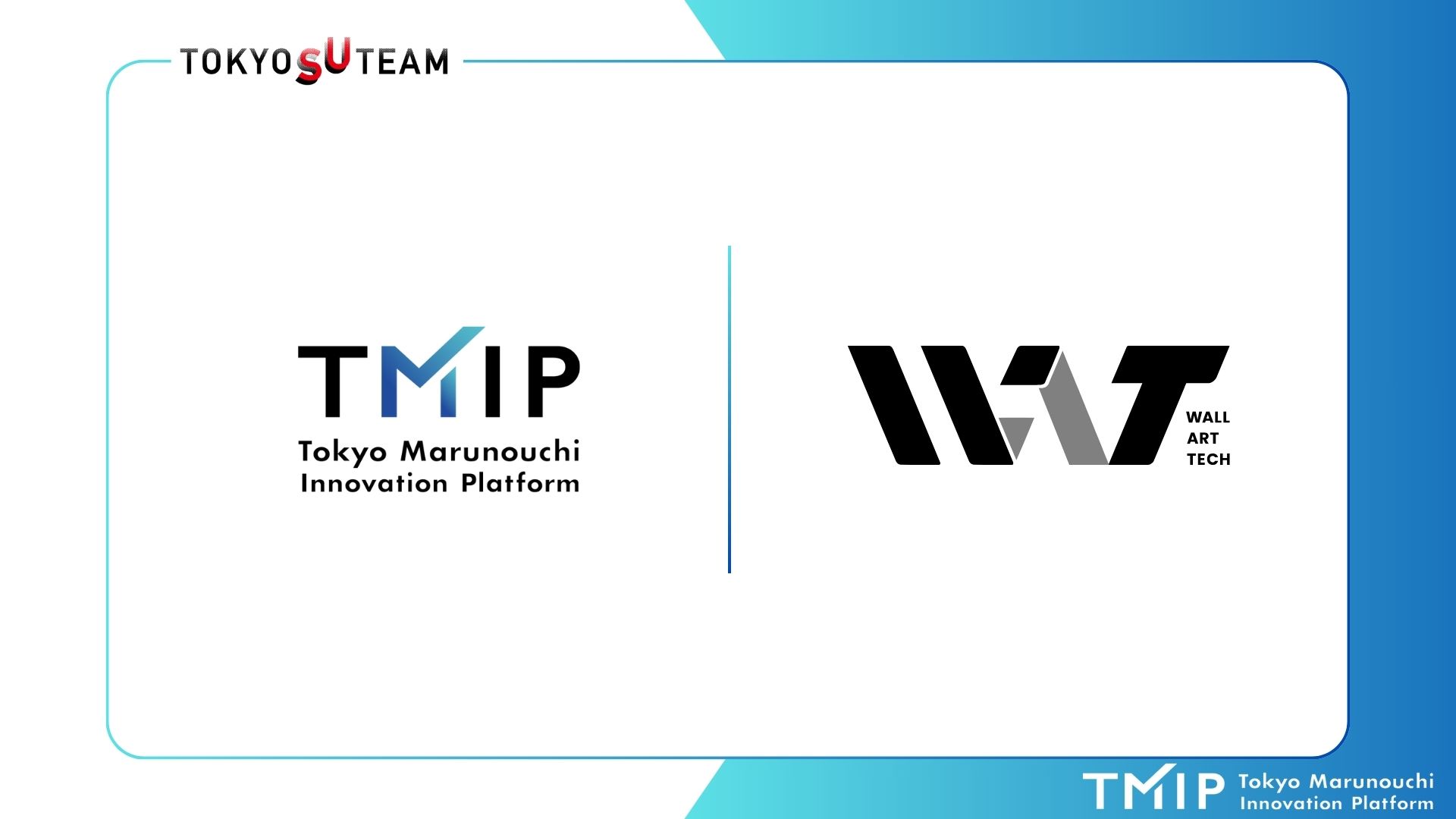岩田 佳子
株式会社リコー デジタルサービス事業本部 プラットフォーム企画センター Pekoe推進グループ グループリーダー
大学院にてヒューマンインタフェースの研究室に所属し、使いやすさ・わかりやすさを軸としたユーザーインタフェースの研究に従事。2002年より株式会社リコーにて複合機の操作部開発を担当。2008年からは社内新規事業部門にてUI/UX設計を中心とした商品・サービス開発を推進。2016年より音声認識技術を活用したサービスの開発に携わったことがきっかけで、働く聴覚障害者の現場の課題を目の当たりにし、2020年以降は「聴覚障がい者向けコミュニケーションサービスPekoe(ペコ)」を新規事業として立ち上げ、誰もが活躍できる社会の実現に取り組む。

増田 拓也
soseki合同会社 代表/CEO
大学卒業後外資系IT企業に入社。海外勤務や海外IT企業の日本法人立ち上げなどを経て2017年セールスフォース・ジャパンに入社。eコマースソリューション事業の拡大に貢献。2020年フェローとして世界経済フォーラム 第四次産業革命日本センターへ派遣。国内のスマートシティ推進支援の傍ら、情報アクセシビリティに関する調査や普及に従事。その後セールスフォース・ジャパンに復帰、社会イノベーション事業創生の活動を立ち上げ社会課題解決とビジネス創出の二刀流に取り組む。2024年soseki合同会社を設立。

白﨑 雄吾
リコーブラックラムズ東京 クラブ・ビジョナリー・オフィサー
2002年リクルートグループ2社を経て、2012年株式会社ビジネス・ブレークスルー(現:株式会社Aoba-BBT)入社。大前研一と共に、次世代リーダー育成プログラムの立ち上げに従事。2017年ビジネス・ブレークスルー大学事務局長。2022年ブラックラムズ東京 クラブ・ビジョナリー・オフィサー着任。現在に至る。
2024年1月、TMIPスタンダード会員である株式会社リコーが旗振り役となり、「アクセシビリティ」をテーマにしたTMIPイノベーションサークル(※1)プレキックオフイベントが開催されました。
それから約1年、アクセシビリティ推進に関心のある事業者や団体が主体的に参加し、共創活動を続けてきたこのサークルの取り組みは、実行フェーズへと移行。その挑戦の第一弾として、2025年3月30日、リコーのラグビーチーム「リコーブラックラムズ東京(以下、ブラックラムズ東京)」とともに『誰もが楽しめるラグビー観戦環境』の実現に向けた「ユニバーサルデー」が開催されました。
本記事では、TMIPアクセシビリティサークルの取り組みと、ブラックラムズ東京との協働に至った経緯、そして両者のアクセシビリティ向上に対する思いに迫ります。お招きしたのは、TMIPスタンダード会員でサークル発起人である株式会社リコー Pekoe推進グループ グループリーダーの岩田佳子さん、TMIPパートナーでサークルを推進するsoseki合同会社の増田拓也さん、ブラックラムズ東京のクラブ・ビジョナリー・オフィサー 白崎雄吾さんです。
両者はいかにして協働に至り、今後、どのような価値を創出しようとしているのでしょうか。

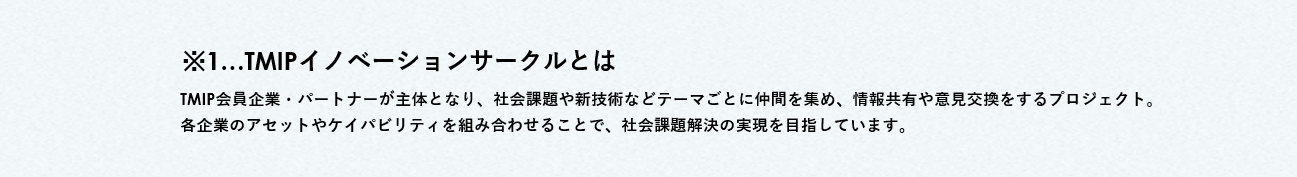
持続可能な活動にするため、「アクセシビリティ」をビジネスに
——まずは、TMIPアクセシビリティサークル立ち上げの経緯をお聞かせください。
岩田:TMIPアクセシビリティサークルを立ち上げ、活動を開始したのは2024年1月のことでした。「アクセシブルな社会を実現するための仲間が欲しい」と考えたことがきっかけです。
私はリコーが2022年8月にローンチした、『聴覚障がい者向けコミュニケーションサービスPekoe(ペコ)』の開発・運営に携わっています。私たちの考えを理解してくださる会社は『Pekoe』を導入してくださるものの、そのような企業はまだまだ少なく、そもそも聴覚障害者がどういうことで困っているのかもあまり把握されていない状況にあることを感じていました。
アクセシブルな社会を実現するためには、この取り組みを理解し、協力している仲間が必要だと感じている中で、2023年の夏にTMIPとTMIPイノベーションサークルの存在を知りました。そこで、事務局の方に「アクセシブルな社会にしていくことに共感してくれる仲間が欲しい」という相談をしたところ、事務局の方がすぐさま会員企業に声をかけていただき、当時セールスフォースで社会課題解決に取り組んでいた増田さんとつないでくださいました。その後、増田さんとアクセシビリティサークルを立ち上げ、約10社の皆さんがTMIPアクセシビリティサークルのプレイベントに参加してくれました。

株式会社リコー デジタルサービス事業本部 プラットフォーム企画センター Pekoe推進グループ グループリーダー 岩田佳子さん
——立ち上げ当初、サークルの目的をどのように設定しましたか?
増田:3つのゴールを設定しました。『アクセシビリティを福祉の観点だけでなく、事業・ビジネスの観点としても捉え、関連する取り組みを発信・実行する場となる』、『アクセシビリティ推進に関心がある方々が交流し活動できるネットワークの場となる』、『2024年に共創による事業実証アイデアを具体化し、2025年に当該アイデアの実証を実施する』の3つです。
特にこだわったのは、「事業・ビジネスの観点でアクセシビリティを捉えること」。アクセシブルな社会は一朝一夕では実現できません。さまざまな企業が、さまざまな形でチャレンジを続けていく必要があると思っています。福祉的な観点からアクセシビリティを捉えることは当然ですが、企業が継続的に活動を続けていくためには、アクセシビリティ向上に向けた取り組みを「ビジネス」にしていかなければなりません。
ですから、TMIPアクセシビリティサークルでの取り組みでは、ビジネスの観点からアクセシビリティを捉えることを重視したいと思ったんです。参加する各社がそれぞれのサービスやプロダクトを持ち寄り、それらを組み合わせることによって、新たなビジネスモデルを構築することを目指し活動を続けてきました。

『Pekoe』を活用すれば、リアルタイムで音声を文字化することが可能に
「体験」をきっかけに、活動を加速させる
——2024年1月にはプレキックオフイベントを開催されました。その後、TMIPアクセシビリティサークルとしてはどのような活動を行っていたのでしょうか。
増田:定例会やワークショップなどを継続的に開催してきました。10人を超えるメンバーがおり、みなさんそれぞれ所属する企業での仕事もあるので、当初は「定例会は2ヶ月に1回程度できたらいいかな」と思っていましたが、実際に活動を始めてみるとみなさんの熱量が予想以上に高く、途中から月1回のペースで定例会を実施していました。
ただ、なかなか共創アイデアが生まれなかった。そんな中で、メンバーから「そもそもサークルメンバー自身が、各メンバーが所属している企業のプロダクトやサービスを『体験』しないと始まらないのでは」という提案があり、その後の定例会で体験会を実施しました。
具体的には、次世代電動車椅子を開発するWHILLさんのプロダクトや、コンピューターサイエンス研究所さんが開発・運営している視覚障害者歩行支援アプリ『Eye Navi(アイナビ)』、オートフォーカスアイウェアを提供しているViXionさんのプロダクトなどをみんなで体験したんです。同じタイミングで共創アイデアを考えるワークショップも実施しました。その日の定例会は3時間にも及び、このことがきっかけとなって活動が前に進み始めた感覚があります。

soseki合同会社 代表/CEO 増田拓也さん
岩田:私は『Pekoe』に携わっているため、ある程度、聴覚障害に関する知識はあるものの、視覚障害や、肢体が不自由な方向けの取り組みや、そのような障害を持つ方々を対象としたプロダクトのことはよく知りませんでした。
実際にTMIPアクセシビリティサークルのみなさんが開発に携わっているプロダクトを体験してみると、その有用性の高さに驚きましたし、より多くの人にそれらのプロダクトを知っていただくことがアクセシブルな社会の実現につながると感じるようになりました。
そして体験会の後のグループワークにおいて、多くの人に各社のアクセシビリティ向上に向けた取り組みやプロダクトを知ってもらうための場として、ラグビーの試合会場を活用する案が浮上したんですよね。
実は2024年4月頃、ブラックラムズ東京の力も借りて、『Pekoe』を活用してラグビーの試合会場で実況を可視化する取り組みを実施していたんです。そういった経緯もあり、ブラックラムズ東京と協力することで、各企業のアクセシビリティ向上に向けた取り組みを知ってもらうための機会をつくれないかと考えるようになりました。
「誰かのため」の取り組みが、「みんなのため」になる
——ブラックラムズ東京としては「アクセシビリティ」というテーマに対し、どのような思いを持ち、どのような取り組みを実施していたのでしょうか。
白崎:ブラックラムズ東京は「Be a Movement.」をチームビジョンに掲げ、スポーツの力を通して社会を動かす存在を目指しています。2021年(実際にリーグがスタートしたのは2022年1月)、「ジャパンラグビー リーグワン」が発足し、社会人ラグビーチームは企業色を抑え、地域に根ざしたクラブを目指し、新たなスタートを切りました。
そのことをきっかけに、私たちもホストエリアである世田谷区や東京都に対してどのような価値を提供できるのかを、深く考えるようになったんです。
アクセシビリティに対する取り組みも、そんな地域社会に対する価値提供の一環です。2023年4月、世田谷区では「世田谷区手話言語条例」が施行されました。以降、世田谷区は手話に対する理解を促進し、手話を使いやすい環境の整備などを進めることによって、聴覚障害者との共生社会を推進する取り組みに力を入れています。我々としてもこの取り組みに協力したいと考えていたところ、リコーの『Pekoe』チームから連携の申し出があったんです。
そうして、『Pekoe』を活用して実況の音声を文字化して、観客が試合を見ながらスマートフォンでその内容を確認できる取り組みを実施。聴覚障害者のみなさんのため、という思いが強かったのですが、試合後、アンケートの結果を見てみると、聴覚障害を持っているみなさまのみならず、あまりラグビーのルールを知らない方々からも「実況を文字にしてくれたことで、ルールがよく理解できた」といった声が多く寄せられました。

ブラックラムズ東京 クラブ・ビジョナリー・オフィサー 白崎雄吾さん
——聴覚障害を持たない方からもよい反応が得られた?
白崎:はい。ラグビーのルールには複雑な部分があり、実況の方もわかりやすく説明してくれているのですが、それでもラグビー初心者には少しわかりにくい。実況が「今のは、ノットロールアウェイという反則です」と言ったところで、聞き慣れない言葉なので、そもそも何と言っているのかが聞き取れない場合もある。
しかし、それが文字になって表示されれば、「ノットロールアウェイと言っていたのか」と気付くこともできますし、その文字がスマホに表示されているので、すぐに調べることもできますよね。その結果、試合をより理解しやすくなるという副次的な効果が生まれたのです。
この取り組みを通して、「アクセシビリティ」とか「ユニバーサル」の本質は、特定の障害を持った方々との共生、包摂を目指してさまざまな工夫をこらした結果、「みんな」がハッピーになることなのだと感じました。
「知ってもらうこと」。すべてはそこから始まる
——2025年3月30日、ブラックラムズ東京の試合が開催された秩父宮ラグビー場にて、「ユニバーサルデー」を開催しました。この取り組みの概要を教えてください。
岩田:TMIPアクセシビリティサークルに所属する各企業が競技場外のイベントスペースにブースを出展し、会場にお越しいただいたみなさまに、各プロダクトを体験してもらうイベントです。
ブースを出展したのは、先ほども触れたWHILLさん、コンピューターサイエンス研究所さんに加え、振動と光によって音の特徴を身体で感じることができる、手のひらサイズのクリップ型デバイス『Ontenna(オンテナ)』を提供している富士通さん、そして、私たちリコーです。
プレスリリース:リコーとTMIP、「誰もが楽しめるラグビー観戦環境」 を目指すブラックラムズ東京の試合にブースを出展します~アクセシビリティを向上し、ソーシャル・インクルージョンの実現に貢献~

来場者がWHILLのプロダクトを体験する様子
——TMIPアクセシビリティサークルとしては、どのような目的を持ってこのイベントに臨みましたか?
増田:ユニバーサルデーは、私たちにとって初の対外的なイベントでした。実行フェーズの第一歩ということで、具体的に事業性を検証するというより、まずは試合会場に訪れるみなさんの「アクセシビリティ」に対する認識を知りたかった。
ですので、会場では「(さまざまな企業、団体の)アクセシビリティに関する取り組みを知っていますか」というアンケートを実施しました。その結果、約半数の方が「知らなかった」と回答し、また「アクセシブルな体験をできてよかったと思うか」という質問については、100%の人が「よかった」と回答してくれました。
まずは「アクセシビリティ」という概念があること、そしてアクセシビリティの向上のために、さまざまな企業がプロダクトやサービスを開発していることを知ってもらうことが重要だと思っていたので、その意味においてこのイベントは成功だったと感じています。
【ユニバーサルデー開催記録】誰もが楽しめるラグビー観戦環境を目指して | Ramsビハインド】
ステークホルダーを巻き込みながら、スポーツを「みんなのもの」に
——ブラックラムズ東京としては、この取り組みを通してどのような気付き、あるいは手応えを得ましたか?
白崎:改めて、多くの人を巻き込むことの重要性を感じました。社会に価値を提供するためには、さまざまなステークホルダーを巻き込まなければなりません。そして、私たちはその「渦」を生み出す存在であり続けたいと考えています。
今回の取り組みでも「巻き込む」ことを強く意識しました。たとえば、今回はブラックラムズ東京のスタッフはもちろんのこと、会場に出店していたキッチンカーのみなさんにも「ありがとうございます」とか「こんにちは」といった簡単な手話を覚えていただきました。

ブラックラムズ東京のファンのみなさんを始め、たくさんの方々が各社のブースを訪れる様子が見受けられました
白崎:もちろん、それで聴覚障害の方々と完璧にコミュニケーションが取れるようになったわけではありませんが、会場にいる多くの人が手話を使うことによって、会場の雰囲気はがらりと変わったと感じています。
手話に限ったことではありませんが、やり慣れていないことを公共の場でやることには気恥ずかしさが伴うじゃないですか。でも、みんなが当たり前に手話を使っていれば、その気恥ずかしさも感じなくなりますよね。多くの方々を巻き込み、手話をつかっていただくことで、「手話を使うことが当たり前」という雰囲気をつくり出せたと思っています。
——ユニバーサルデーに訪れた方々からは、どのような反響が寄せられましたか?
白崎:本当にさまざまな声が寄せられましたが、その中でも特に印象的だったのは、介助が必要な方のご家族の声ですね。この日は、実にさまざまな方にお越しいただき、その中には全介助(日常生活の動作全般に介助が必要な状態)の方もいました。
その方のご家族にお話を聞くと、「この子が生まれたときは、家族みんなでラグビーを見に来ていたんです。でも、この子に障害があるとわかってからは、ラグビーを見に行くこともなくなってしまった。本当に久しぶりのラグビー観戦で、家族みんなで興奮したし、夢のような時間だった」と。
そうお話する様子が、本当に嬉しそうだったことが印象に残っています。私自身、改めてスポーツの力を実感しましたし、スポーツをもっと「みんなのためのもの」にしていかなければならないと思いました。
「想い」を伝え合うことが、共創を加速させる
——サークルの立ち上げから、実行フェーズの第一歩であるユニバーサルデー実施までのプロセスを通して感じた、会社の壁を越えた共創におけるポイントを教えてください。
増田:「想い」を共有すること、ですね。
この1年を通して、改めて共創は「言うは易く、行うは難し」だと実感しました。立ち上げ時に掲げた、「アクセシビリティを事業・ビジネスの観点としても捉え、関連する取り組みを発信・実行する場」にすること、そして「2025年に共創によるアイデアを実証する」というゴールは、正直まだ遠いと思っています。
一方で、所属する企業の規模も業種も、それぞれの想いも異なる多様なメンバーが集う中で、全員が忙しい仕事の合間を縫って活動に参加し、共同でのイベント出展というアウトプットにつなげられたことは、大きな一歩です。そして、そのアウトプットを生み出したのは間違いなくみなさんの「想い」だと思っています。

——サークルを運営する立場として、みなさんの熱量を保ち、想いをつなぐために心がけていたことはありますか?
増田:直接顔を合わせることですね。定例会はオンラインで実施することもありましたが、なるべくオフラインで膝を突き合わせてコミュニケーションをすることを大事にしていました。やはり、直接話すことでしか伝わらないことってあると想っていますし、直接それぞれの「想い」を共有したことが、サークルの活動を前に進める原動力になったと思っています。
共創を生み出す「ハブ」としてのTMIP
——TMIPアクセシビリティサークルとブラックラムズ東京の、今後の取り組みについて教えてください。
白崎:「ユニバーサルデー」の取り組みとして、約300名の方をご招待しました。TMIPアクセシビリティサークルとの取り組みの第一歩としては、とてもいいスタートが切れたと思っていますが、ブラックラムズ東京としてもよりたくさんの方に「アクセシビリティ」に目を向けてもらいたいと思っています。
だからこそ、来シーズン以降もTMIPアクセシビリティサークルと協力して、ユニバーサルデーを続けていきたい。来シーズン以降は、先ほど紹介したような、障害者のみなさんやそのご家族など、スポーツを観戦したくても観戦できなかった方々をもっとたくさんお招きしたいと思っています。

岩田:TMIPアクセシビリティサークルとしては、サークルに参加してくれる企業を増やしたいと思っています。想いをもった仲間が増えれば、新たな取り組みが生まれやすくなりますし、認知拡大にもつながるはずです。
そうして、障害を持つ方々に対する社会の目線を変えていきたいと思っています。今回のユニバーサルデーには、たくさんの子どもたちも参加してくれました。将来を担う世代が、早いうちから「アクセシビリティの向上」というテーマに触れていれば、いつか社会に飛び出したとき「どのような人とでも共に働き、暮らすことができる」と信じられるようになるはずです。
アクセシブルな社会を実現するために、ユニバーサルデーのような取り組みを通じて、その重要性をたくさんの人に伝え続けたいと思っています。
増田:TMIPアクセシビリティサークルとしての究極のゴールは、社会から「アクセシビリティ」という言葉がなくなることだと思っています。つまり、アクセシビリティに配慮することが当たり前の状態になり、すべての企業あるいは個人が「アクセシビリティが重要だ」と意識することなく、さまざまな事物がアクセシブルなものになっている状態が理想です。
もちろん、簡単なことではありません。でも、その状態を実現するためにはできることからやっていくしかありません。細々とでもいいから、続けていくことが重要だと思っています。だからこそ、アクセシビリティをビジネスの観点で捉えることにこだわり、TMIPアクセシビリティサークルの活動を持続可能なものにしていきたいと思っています。
——白崎さんから見て、TMIPアクセシビリティサークルの価値をどのような点にあると思っていますか?
白崎:アクセシビリティという概念を社会に広げていることはもちろんなのですが、いちビジネスパーソンとして言えば、1つの窓口とやり取りをするだけで、さまざま企業とのコラボレーションが可能になる点は大きいと思っています。
スポーツの価値とは、「ボンド」と「アンプ」だと言われることがあります。つまり、スポーツには、人と人、あるいはコミュニティとコミュニティを「つなげる」効果と、何らかの概念や思いを「増幅させる」、言い換えれば「広げる」効果があると言われているんです。だから、スポーツチームである私たちとしては、企業のみなさんにそんなスポーツの力をうまく使って欲しいと思っています。
ですが、私たちのリソースも限られているので、同時に複数社と協力することは簡単なことではありません。今回のユニバーサルデーでは、4社がブースを出展しましたが、もし4社と個別にやりとりをしていたら、その調整にはかなりの工数が掛かったと思うんです。
TMIPアクセシビリティサークルという一つの窓口があったことによって、連携に要するリソースは大きく削減できました。さまざまな企業、団体、あるいはチームが協働し、新たな価値を生み出すことが重要だとされている中で、TMIPのような団体が果たす役割は大きいと思います。